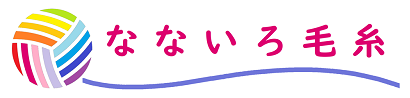こんばんは、細野カレンです。
週の終わり、少し空気が静まってくるこの時間に、編みかけの糸をそっとひらいてみると、きょうの光と、手のぬくもりと、ほんの少しの感情が、そこに編みこまれているような気がします。
そんな静けさの中で、ふと目に入るのが、毛糸に織り込まれた小さなきらめき――
スパンコールという素材には、実はとても古くて、長い物語があるんです。

金貨から生まれた、光のかけら
スパンコールのはじまりは、古代エジプトまでさかのぼります。
ツタンカーメン王の衣には、純金の小さな円形が縫い付けられていたそうです。装飾というよりも、それは王の身分と富の証。
万が一の旅立ちに備えて、“身につけられる貯金”のような意味合いがあったとも言われています。
衣服に貨幣を縫い付けるなんて、ちょっと奇妙に思えるかもしれませんが、それだけ「持っていること」が大切な時代だったのでしょうね。
刺繍やビーズにお守りの意味をこめる文化はいまも各地に残っていますが、あの輝きには、そんな祈りのような感覚が宿っていたのかもしれません。
その後中世ヨーロッパでは、ヴェネツィアの金貨「sequin(スカン)」が広く使われました。
この言葉が、現代の「スパンコール」の語源になっています。

舞台の上の輝きから、日常へ
20世紀初頭、スパンコールはオペラやレビュー、バレエの衣装に欠かせない存在となりました。
照明のもとで小さな動きにも反応して光を反射するスパンコールは、まるで“光を踊らせる布”のよう。
当時の衣装デザイナーたちは、ひとつひとつのスパンコールを手縫いで縫い留めながら、「光がどのように走るか」を計算していたといいます。
けれどそのころのスパンコールはまだ金属製で、とても重たく、ドレスを着て踊るだけで一苦労。踊りの途中でスパンコールがはじけ飛び、観客席に落ちることもあったそうです。
それでも人々は、「舞台の光が降ってきた」と言って、それを拾い、お守りのように持ち帰った――
そんなエピソードが残っているほど、光には特別な意味がありました。
やがて素材はプラスチックに変わり、衣装は軽く、身近なものになっていきます。
でも、光をまとうという本質は、今もずっと変わっていません。

手の中で揺れる、小さな光
いまのスパンコールは、毛糸にそっと織り込まれ、控えめに、でも確かにきらめきます。
たとえば「派手すぎるのは苦手。でも、地味すぎるのも…」そんな気持ちのとき、引き揃えて編むことで、ふだんの編み地にひとすじの光が加わります。
素材そのものが軽く、やわらかく、やさしい手ざわりの中に輝きを宿す。
日常の編み物の中に、スパンコールが静かに溶け込んでいることの意味。
それは、ただの飾りではなく、編む人がまといたいと感じる小さな記憶なのかもしれません。

光の意味を知ると、選び方が変わる
その小さな輝きが、どこから来たものなのか。
どうしてそこに惹かれるのか。
知れば知るほど、「この糸を使いたい」という気持ちに、深い理由が生まれてくる気がします。
ノヴィータ ヴァロも、そんな一本です。
ノヴィータ ヴァロの詳細はこちらでご覧いただけます
ノヴィータ ヴァロ 商品ページ
手の中で光る小さな粒に、少しだけ目を留めたくなる夜。
あなたの次の編み物が、ほんのりと、心に残るものでありますように。